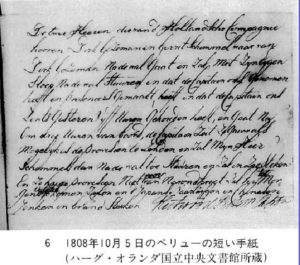フェートン号が出港してから25日目の1808年8月3日、マドラスに東インド会社の商船10隻が到着した。
5か月の航海を経て、渡洋シーズン最初の船団の到着である。次々と放たれる礼砲の轟音に沸き返る街の前面に広がる砂浜に、船団から椰子の木で作られたマスーラ船に乗せられて半ばずぶ濡れになって船客が上陸してくる。マドラス総督George Barlow卿
の妻Lady Barlowはその中で格別の賓客であった。彼女は二人の娘を連れて2年ぶりにインドへ戻って来たのだ。17日、地元新聞Madras Courieが『Barlow夫人歓迎の宴を26日エドワード・ペリュー提督が開催』とのニュースを報じた。当日の夕方、港やセントジョージ要塞を見下ろすMount Roadマウントロード(Mountと言っても高地ではない。平坦なマドラスでは丘のような高さ。
標高18ⅿ)のインド艦隊司令長官公邸Admiralty Houseへは数多くの輿Palanquinや馬車に乗って地元の知名士達(もちろんイギリス人社会の!)が集まってきた。
その中にはインドに住むイギリス人の中で一番の長者と言われるWilliam Hope(彼は英陸軍の一兵卒から貿易商に転じ巨万の富を得た)を始めとするNabobsネイボッブが顔を揃えた。Nabobsとは『インド成金』のことである。Hopeに代表されるように家柄も教育もなく、欲望剥き出しで熱帯の地で巨万の富を築いた彼らは、母国では羨望と嫉妬と侮蔑の対象であった。母国では考えられないあらゆる贅沢が彼らには可能であった。数十人の召使を雇い(必要なら百人以上雇っても毛ほども家計負担にはならなかったろう)、巨大なバニヤンツリーの日陰が庭を覆う大邸宅に住み、贅の限りを尽くして遊び惚けた。洗練とは縁のない欲望剥き出しの世界だった。二階建ての植民地特有の白い建物(シンガポールのラッフルズホテルにその典型を見ることが出来る)
は広いホールから二階へ続く広大な階段があり、天井は高く、すべての窓はラタン製のベネシアンブラインドが陽を遮っていた。そのブラインドには冷却効果のために常に召使が水を注いでいる。
樹木に囲まれたドライブウエイの先にはひと際威容を誇るインド艦隊司令長官の公邸Admiralty Houseがあり、広大な前庭は輿や馬車で埋まっていた。客たちが階段を昇って一階のホールへ入ると、海軍提督と海軍士官の正装に身を飾った長身の二人の男が満面の笑みで迎えた。エドワード・ペリュー提督と長男の海軍士官Pownolである。モンスーン初期のこの夜は気温40度、分厚い羅紗の青い軍服とバックスキン製の白いトラウザーをまとったエドワード・ペリュー提督は汗まみれであった。今や肥満体の彼はインドの暑さが苦手だった。しかしそれでもインド在住の当時のイギリス人は半袖や短パンのようなコスチュームを導入しなかった。恐らく現地のインド人に対するイギリスの正装が彼らの特権意識を表現していたからではないか、と思われる。羅紗地の服が権威と富の象徴だったのだろう。インドの支配階級が同じく絹の正装に身を包んでいたこととも無関係ではあるまい。

この夜のスターはLady Barlowだった。自分が頂点に立つ社会に戻って来たせいだろうか、飽くことなく踊り続けた。真夜中にようやく夕食が供されたが、彼女を取り巻く踊りの輪は朝まで続いた。たとえ汗まみれになってもインド人の召使たちが丁寧に洗いアイロンをかけ、食事は好きな時に供される生活なのだ。労働には一切手を染めない驕奢の街の住人たちである。エドワード・ペリュー提督の酒量もまた底抜けであった。
そういう中でLady Barlowとエドワード・ペリュー提督の目論見が見事にうまくいった。Lady Barlowの娘Elizaとエドワード・ペリュー提督の長男Pownolが互いを見初めあったのだ。エドワ-ドは周囲の顰蹙の目を気にもせずPownolを若くして士官に、そして艦長に取り立てたがPownolが血生臭い戦闘よりも恋愛にずっと関心があることを見抜いていて、コネと富に恵まれた結婚相手を探していた。Lady Barlowにとっても、インド艦隊の司令長官として捕獲した賞金の分け前を8万ポンド(現在に換算すると約7億円の価値。Stephen Taylorの”Storm & Conquest”より)も所有し、貴族に列せられたエドワード・ペリュー提督の長男との婚約は申し分なかった。イギリスから5か月の航海を経てインドまで連れてきた成果である。 Lady Barlowと同じ船団にはNabobsとの結婚を夢見てfishing fleetと呼ばれる適齢期の女性たちも大勢やってきた。文字通りなら”魚釣り艦隊”だが、この場合は”花婿狩り艦隊”とでもいうべきか。現代なら富豪二世や医師の卵との合コンに参加して未来の旦那様をゲットしようと目論む若い女性のようなものだろう。彼女らもこの夜、朝までエネルギッシュに踊り狂ってこれはというNabobsを物色していたろう。というのもFishing Fleet花婿狩りの女性たちにとってElizaとPownolのようなあっという間の婚約は当時珍しいことではなかったのである。西部開拓時代のアメリカのような女旱(ひでり)がひどかったのだろう。男たちも自分の嫁を見つけるのに血眼だったに違いない。
Lady Barlowと同じ船団にはNabobsとの結婚を夢見てfishing fleetと呼ばれる適齢期の女性たちも大勢やってきた。文字通りなら”魚釣り艦隊”だが、この場合は”花婿狩り艦隊”とでもいうべきか。現代なら富豪二世や医師の卵との合コンに参加して未来の旦那様をゲットしようと目論む若い女性のようなものだろう。彼女らもこの夜、朝までエネルギッシュに踊り狂ってこれはというNabobsを物色していたろう。というのもFishing Fleet花婿狩りの女性たちにとってElizaとPownolのようなあっという間の婚約は当時珍しいことではなかったのである。西部開拓時代のアメリカのような女旱(ひでり)がひどかったのだろう。男たちも自分の嫁を見つけるのに血眼だったに違いない。
10月1日、Pownol Pellew とLady Barlowの娘Elizaとの結婚式が盛大に開催された。Pownolは21歳、EliZaは19歳、インドを代表する二つの権威、インド艦隊司令長官家とマドラス総督家の結婚である。Pellew提督とBarlow総督は二人にそれぞれ2万ポンド(現在の価値は1.75億円に相当する。二人合わせると3.5億円、インド住まいのイギリス人たちの凄まじい富の集積を体現している!)を与えた。この式に次男フリートウッド・ペリューは出席していない。彼はフェートン号の艦長として遥か東シナ海にいて長崎港に突入寸前の日々を送っていたのだ。当然、当時の通信事情ではエドワード・ペリュー提督もPownolも彼が日本の近海にいるだろうと漠然と予測しているだけである。エドワード・ペリュー提督は次男フリートウッド・ペリューの任務実施の状況を知ることは出来ないが、長男Pownolが結婚したことで、海軍士官としての資質に欠けるPownolの将来設計が最良の形で出来たことになる。次男フリートウッド・ペリューは彼に与えた遠征任務がうまくいけば海軍士官としての洋々たる将来が開けるはずである。残るはエドワード・ペリュー提督自身の将来設計である。この頃の彼の手紙には次のような文章がある。
“(髪は)アライグマのような灰色になり、豚のように太って腹の突き出た(私)”と自虐している。暑いインドは苦手だし、何より愛妻スザンナとはマドラスに赴任した1804年以来もう5年も離れ離れの生活なのだ。Admiralty海軍省にさんざん働きかけたことが実り、ついに後任人事が発令され、彼には本国帰還命が出たのだ。後任はWilliam Drury、エドワード・ペリュー提督と同じ1804年に海軍少将に任ぜられている。だが彼の着任は遅れに遅れた。彼もまた歴戦の勇士である。彼は1808年エドワード・ペリュー提督の後任としてインド艦隊司令長官に任ぜられたが、その際アフリカ南端の喜望峰を管轄する艦隊の司令長官も兼務したが、喜望峰の前任者Bertieとの司令権限を巡って二人は激しく対立し、Admiralty海軍省も手を焼くほどだった。インドへの出発が遅れたDruryはBertieとの対立もそのままエドワード・ペリュー提督の任務を引き継ぐべくインドへやって来たが、エドワード・ペリュー提督は彼の着任が遅れたのでカルカッタ経由でマレー半島の)ペナンへ向かい、そこでDruryと任務を引き継ぐことになった。
ここで読者の皆さんにはまことに申し訳ないが、この物語の『10 マラッカ』で記しているようにフリートウッド・ペリュー率いるフェートン号は7月の末、マラッカにいる。しかしエドワード・ペリュー提督の行動上、ここでは10月以降の展開をお許しいただきたい。混乱されるとは思うがご容赦いただきたい。
乗艦はインド艦隊の旗艦Culloden、砲74門搭載の堂々たる戦列艦(艦隊同士の決戦用に設計された砲70門から120門を備える巨大戦艦)である。艦長はPownoll Pellew、ペリュー提督の若き長男である(この時22歳。戦列艦を率いるにはいかにも若い)。ただ、このあと翌年3月Cullodenがインドからの船団を率いて帰国の途上ハリケーンに遭遇して船団もCullodenも大被害を被った際の航海日誌には“Pownoll艦長とthe masterが操船指揮”(Storm and Conquest)とあることから老練なmaster(masterはRoyal Navy誕生以前の船長の称号であった。Royal Navyが成長するにつれ、Captain艦長の呼称は戦闘指揮を行う海軍艦艇指揮者を指すようになる(“7 日誌記録者ストックデール”参照)。Cullodenの場合は、master=航海長という感じだろうか)。CullodenにはPownollの新妻Elizaも乗艦していた。この事実と言い、かつてエドワード・ペリューが若き頃乗艦していたJunoでStott艦長が情婦を乗艦させていた件(“11 ペリュー艦長の父“参照)と言い、日本海軍しか知らない日本人には実に不思議というしかない光景である。
それはともあれ、父と長男は10月24日にBengalへ向かって出航、風向きのせいで3週間かけてカルカッタへ到着、ここで2週間にわたりインド総督と離任の宴を繰り広げた。12月6日、後任のDruryが待つマレー半島のペナンへ向かった。Druryとともに待っていたのは日本遠征を終えたフリートウッド・ペリュー、フェートン号の艦長である。(再び言うがこの物語ではまだマラッカにいるフェートン号の5か月後の姿である)
父と次男フリートウッド・ペリューは7月9日のフェートン号マドラス出航以来半年ぶりの再会の筈だが、Stephen Taylorの“Storm and Conquest”には何のコメントも無い。”Storm and Conquest”はエドワード・ペリュー提督を軸にインドとインド洋を舞台にしたドキュメント大作であるがにもかかわらず、である。これは次男フリートウッド・ペリューに日本遠征を命じたエドワード・ペリュー提督の真意に関わってくるので、後に詳細に論じたい。この時、長男Pownolの新妻Elizaとフリートウッド・ペリューは初めて会ったのだが、Elizaは自分の夫の弟を見て一目惚れしたようだ。フリートウッド・ペリューはハンサムぶりに傾倒したのはElizaだけではない。この年のイギリス本国へ向かう船団の一つに乗船していたある夫人は『これほど美しい男性を見たことはない』と驚嘆したと日記に書き記している(“Storm and Conquest”)からElizaがうっとりしたのは間違いないようだ。ペナンでそれがどう発展したのかは何らわからない。やがてCullodenはインドからイギリス本国へ向かう第2船団を護衛するためにセイロンへ向かい、翌1809年2月セイロンのゴールで船団と合流することになる。ペリュー親子がマドラスを出航した2日後の10月26日、インド洋を西へ向かって吹く貿易風シーズン到来を待ち望んでいた東インド会社の第1船団9隻がフリゲート艦Albionに護衛されてケープタウンへ向け出航した。
各船800トンから500トンの積載量だがそれぞれ船腹一杯の硝石を積載している。当時ポルトガルでナポレオン軍と戦っている英陸軍の火薬補給のためだ。過積載に近いためノロノロと進むこの第1船団はマダガスカル沖で発生するハリケーンの只中に突入して大被害を被ることになる。
第2船団はそれから数か月後にもかかわらずハリケーンシーズンはまだ真っ盛りでエドワード・ペリュー提督のCullodenも辛うじてケープタウンへ到着したが、第1船団9隻、第2船団18隻のうち、◦隻が遭難して沈没するという事態になった。英軍の兵卒からインド随一の富豪と言われるほど成功したNabobの第一人者William Hopeもまた、本国へ持ち帰る莫大な財宝とともに海の藻屑と消えた。なお現在はインド洋ではサイクロン、太平洋ではタイフーン、カリブ海ではハリケーンと呼び方が変わるが、この当時はすべてハリケーンと呼んでいたそうである。



ペナンに残ったフリートウッド・ペリューは父の後任Druryドゥルーリー提督とともにフランス艦の捜索任務にあたったがDruryのフリートウッド・ペリュー評は誠に辛辣で『命令を受けるということの認識や理解が極めて乏しい』と酷評して、暗に父エドワード・ペリュー提督の甘やかしとえこひいきによる早すぎる昇進を批判している。このDruryは先述したがケープタウンをイギリスがオランダから奪い取った後のケープタウン海軍基地の司令官となったがBertie提督との共同司令官をAdmiraltyが発令したため、DruryとBertieとは激しく憎みあい、お互い一歩も譲らず軍法会議に提訴しあうほど対立した。この当時のAdmiraltyはこのような共同司令官を発令するという奇妙な軍政が見られる。同じことが実はエドワード・ペリュー提督にも起こったのだ。1804年インド艦隊の司令長官に就任したエドワード・ペリュー提督の後を追って、Tourbridge提督が同じ職位に発令されたのだ。エドワード・ペリュー提督は憤激し、『こういう(自分の)名誉を汚すことがお行われるのなら(自分は)本国へ帰国してフリゲート艦の艦長になる』との強硬な文書をAdmiraltyへ送ったのでTourbridge提督の職務重複はのちに解消した。このことでエドワード・ペリュー提督とTourbridge提督の間柄も終生の敵同士となる。このような重複人事の発生はAdmiralty内の派閥によるものらしいが現時点では筆者には詳しいことは分かっていない。いかにも発展途上の海軍らしい出来事である。
それにしてもDrury提督 vs Bertie提督、エドワード・ペリュー提督 vs Tourbridge提督の対立と憎悪の激しさは、どうしたものだろう。官僚制度が確立した現代の軍制度では到底想像のつかない剥き出しの荒々しい個性の対立である。個人の個性や人格が容易に反映された英雄時代の海軍であった、ということだろうか。
(この章の歴史的事実の殆どはStephen Taylorの“Storm and Conquest”に依拠しています)