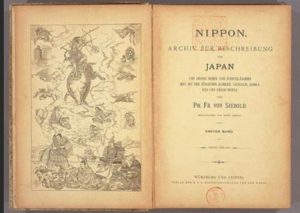近藤重蔵(じゅうぞう)は1771年(明和8年)小身旗本(御先手組与力)の三男として生まれた。家禄は250石足らずと推定される。当時の徳川幕府家臣団は約8万人、今の都庁職員は16万人、御先手組与力(戦乱となれば槍または鉄砲で先陣を切る足軽団)は町奉行与力よりは位が高かったというから、重蔵の生家は都庁でいえば古参係長か課長級クラスであったろう。幼少期から神童の誉れ高く、8歳で四書五経を諳んじ、17歳で私塾を開き、生涯で記した本が1500余巻という(近藤重蔵wiki)から現代でも滅多にお目にかからない神童だった。「1794年(寛政6年)松平定信の行った湯島聖堂の学問吟味に合格」(同上)したことで優秀さがお墨付きになっただろう。この近藤重蔵を日本史上で普及の名前にしたのは自ら志願した北方調査で千島列島や択捉島を探検し、択捉島に「大日本恵土呂府」の木柱を立てたことである。ソ連そして今はロシアが不法に占拠する北方領土の日本帰属を確実にした近藤重蔵はいま泉下で悔しがっていることだろう。



この大偉業に先立つ1795年(寛政7年)、重蔵は長崎奉行手付出役として長崎に赴任する。なぜこの年に幕府が秀才の誉れ高い重蔵を長崎へ送り込んだのか?それは当時の商館長ヘンミイと島津重豪の間に抜け荷の疑いがあることを解明するためだった。長崎奉行として赴任したばかりの中川飛騨守忠英(ただてる)は後に幕府大目付という要職に登り詰めた能吏であるが、歴代の長崎奉行の課題である薩摩藩の抜け荷が島津重豪という将軍家の岳父である超大物によりのっぴきならない段階まで来ていることを突き止めるために重蔵を抜擢して長崎奉行手付出役(しゅつやく。現代の出張/出向にあたる)として配下に置き、目安方(民事刑事訴訟に携わる一方で隠密、探索などが本務の役職)に据えた。重蔵は2年半の長崎在勤中に唐人屋敷、オランダ商館を頻繁に訪ねて中国関連では清俗紀聞(8冊)、オランダ関連では紅毛書(5冊)などを編纂しているが、これ等の作業はオランダ商館へ立ち入るための口実であり、実はヘンミイが画策している抜け荷の証拠を掴むためであった。オランダ商館で疑われずに捜査に当たるために海外事情調査と称して唐人館に出入りして(これはオランダ商館が主目的と見破られないため)清俗紀聞を編纂し、同じことをオランダ商館で「紅毛人へ本草、物産類の儀、相尋ね」(近藤重蔵自身の勤書=履歴書。「抜け荷」山脇悌二朗122p)、紅毛事情としてまとめるためという口実でオランダ側の警戒を緩め、あらゆる書類にアクセスしたと思われる。



商館のNo2はドゥーフが能力を見限った例のラスだから重蔵にとっても仕事がしやすかった面があるかもしれない。そして重蔵はまさに期待された通りの成果を上げる。小通詞末席の名村恵助とヘンミイの間で交わされた密かな計画の探知である。その内容は水戸の史館総裁であった立原翆軒がオランダ大通詞であった楢林重兵衛から聞いたという話として残っている。すなわち、「蘭船二艘来るうち一艘は海中にて中買せんとの約束の文なり」(「抜け荷」山脇悌二朗115p)というのだ。「海中(海上)にて中買(仲買)」となればそれが可能なのは薩摩藩しかない。何度も書いているが、南から北上するオランダ船は長崎よりも先に薩摩領に立ち寄ることが可能だからだ。商館長自身が絡んだこの恐るべき計画の探知時期は重蔵の長崎赴任中の最後の頃だと思われる。極めて優秀な重蔵の頭脳をもってしても清俗紀聞8冊や紅毛書5冊の編纂をするには2年は必要だったろう。2年半以上が過ぎた1797年末(寛政9年)に重蔵は長崎赴任を終えて江戸へ戻る辞令が出る。すなわち動かぬ証拠を見つけたからこれ以上の長崎奉行所での勤務の必要がなくなったのだ。では近藤重蔵が探索を命ぜられた島津重豪とヘンミイの計画とは何だったのか?まず島津重豪の事情から見ていこう。前の章で触れたように重豪は新たな借財のために大阪の商人と直接会って掛け合うほどに金策に懸命だった。500万両にまで積み上がった借財は必ずしも重豪のせいではないとの説(「島津重豪」芳即正)もあるが、重豪の統治下で進められた数々の事業(造士館、演武館、医学院、明時館等の創設)、熱中した鷹狩り、蘭癖大名と呼ばれた舶来品への執着と収集、高輪(重豪)と白金(近思録崩れで重豪に隠居させられた斉宣)の二つの隠居御殿の維持、などいずれも金のかかることばかりである。大阪商人との直交渉に出馬したのもそれを自覚していたからこそであろう。歴代の商館長と深い付き合いがありヘンミイも例外でなかったから、重豪はヘンミイの窮状を知りお互いが協働することでヘンミイにも薩摩藩の財政危機にも役立つと思ったのではないか。ヘンミイの窮状とは、「15 スチュワートの登場」でみたように「銅」である。日蘭貿易による昔日の巨大な儲けは今や昔話となり、薩摩藩と同じように積み上がった借財で財政危機にあったオランダ東インド会社にとって唯一の解決策は莫大な利益をもたらす日本の銅であった。

だが松平定信の寛政の改革でオランダへの銅の輸出額は年20万斤にまで大幅に削減されていた。スチュワートの章で明らかにしたように1797年1798年にオランダ商館が仕入れた銅は現代の価値で9億円から18億円程度である。ヘンミイは前商館長から買い付ける銅の量を増やすことが最大の任務だと厳命されている。忠良なる東インド会社員としての義務だけではない、オランダ東インド会社の儲けは直接自分の功績となり、付随して自分の富を蓄積できることにつながる。だから商館長たちは必死だった。それに重豪は気が付いたのだろう。15章で触れたように薩摩藩は銅を動かせる。薩摩藩御用達の大阪商人を使うのである。「大坂三郷の総年寄薩摩屋仁兵衛は、大坂で薩摩の国産物を扱う随一の問屋でもあり、薩摩蔵屋敷の蔵元でもあったから、薩州国産物を捌いた代金を銅銭で受取り、ないしはそれで銅を買求めて(大阪銅座は毎年九十万斤ほどを国内用にリザープしていた)、かれに送らせればよかった。」(「抜け荷」山脇悌二朗126p)という構図であった。仁兵衛は薩摩が密かに手に入れる唐物の販売を手掛けてもいたから(当然これは抜け荷行為である)重豪の頼みには二つ返事であったろう。ヘンミイにしてみれば仁兵衛が動かせる大阪銅座の九十万斤から融通してもらえれば、幕府割り当ての20万斤の二倍や三倍の銅をバタビアへ送り出せることになる。重豪と仁兵衛にしてみれば、幕府(長崎奉行所と長崎会所)が卸す銅価より高い値付けをすればよい。銅を国内市場用からヘンミイに横流しすれば、儲かることになる。ヘンミイは高い銅を仕入れても、結局欧州市場ではもっと高値で捌けるのだ。これは三方一両得のwin win関係になる。問題は受け渡し方法であった。それが蘭船二艘のうち一艘が「海中で中買」するということになったのだろう。
このようなスキームはどう構築されていったのか。そこを解明したのが近藤重蔵である。当時、今籠町という町があった。ここには通詞や出島での雑用などに関わるものが多く住んでいた。のちに 1828年(文政11年)シーボルト事件が起こった時に処罰された小通詞や稽古通詞たちもこの今籠町に住んでいたから、通詞町と言ってもよいような町だったろう。通詞は長崎のエリート階級である。舶来品やオランダ語の会話が行き交うエキゾチックな街だったろうと想像される。だが明治大正昭和の街区整理や町名変更により、今籠町は今の長崎には存在しない。町名は昭和41年に鍛冶屋町に吸収され、今籠町くんち奉賛会の働きにより諏訪神社例大祭の「おくんち」の踊り町として平成21年に復活した。古地図によると今石灰町の東側、崇福寺と大光寺の辺りになる。正確には当時どこにあった町なのか?この疑問に答えてくれる素晴らしい復元図が長崎文献社より2009年(平成21年)出版された。『長崎惣町復元図(布袋厚氏作成)』である。同氏は今も残る「長崎惣町絵地図」(十畳間の大きさの明和年間に作られた精密な測量図。)と様々な古地図を基に詳細な現地調査と数式をも使った実に緻密な照合作業で、現代の地図の上に正確に昔の長崎の街を復元したものである。この作業を解説したのが『復元!江戸時代の長崎 布袋厚』という著書である。布袋厚氏の偉業によって今籠町の場所とサイズが現代によみがえった。布袋氏の復元図によれば、思案橋の交差点から北へ寺町通りに向かって歩き、左に銀嶺を見る五差路の交差点、ここが起点である。角には花屋さんもあり、なんとなくパリの街角を思わせる華やかな雰囲気である。ここから右手に崇福寺(唐寺、国宝)へ向かって伸びる緩い上り坂。これがほぼ元の今籠町である。現在の車道の真ん中に昔の通りがあったと考えられる。その幅は、今の歩道程度であったろうか。
現在の今籠町を見てみましょう。
布袋氏の地図によれば、通りを挟んで東西の幅60m、南北の長さ約190ⅿの町である。これは銀座で言うと、銀座4丁目(晴海通りからみゆき通りまで)の2ブロック程度になる。面白いことにこれは出島のサイズにとても近い。出島は東西180ⅿ、南北73mと考えられている。出島は長崎の町と似たようなサイズで設計されたことが類推される。出島の中には65軒の建物があったそうだが、倉庫や西洋式の大型の家屋が多いので、今籠町は100軒ほどの日本式町屋があったのではなかろうか。当時の人口は定かではないが、現代と違ってプライバシーという概念も無く濃密な人付き合いが当たり前で人別帳(戸籍)もあった江戸時代にはどの家に誰が住んでいるか皆が知っていた。ここに今籠町トライアングルと言っても良い3人が関係を結んだ。一人は堀門十郎。島津重豪とつながる通詞である。もう一人は名村恵助。小通詞末席という通詞社会の中堅だが名門名村家の一員である。町家を所有していたろう。最後の一人が忠蔵である。姓が無いのでわかるように、出島に出入りして雑用を引受ける下働きである。言わばヘンミイの召使であった。これは長屋住まいだったと考えられる。
堀門十郎は3人の中では一番の大物である。近藤重蔵が秘密任務のため長崎入りした1795年(寛政7年)に既に経験豊かな大通詞であった。大通詞は通詞社会のトップに君臨し、年番大通詞(年の当番を務める大通詞)の時にはオランダ商館長の江戸参府に同行する。オランダ船が入港すれば商館長とともに風説書を作成するという国家機密の作業にも従事する。「堀門十郎は天明三年三月三十日、楢林重兵衛が大通詞に昇進したあとをおそって小通詞にすすみ、寛政元年には年番大通詞を勤めているから、天明八年ごろ大通詞に昇進したものであろう(『年番通詞一覧』「島津重豪」芳即正144p)」という。15章で紹介した大通詞の収入は年三千両(テール)という情報は、元禄年間にオランダ商館付き医師として来日したドイツ人ケンペルが書いた話である(「阿蘭陀商館物語」宮永孝48p)。堀川門十郎は、今籠町きっての豪邸に住んでいたことであろう。ただし元禄年間は日蘭貿易が盛んで長崎の貿易バブルが絶頂期の頃である。人口も長崎奉行管轄地で5万6千人であったし、丸山町寄合町の傾城町は千人もの遊女で賑わっていた。
 この物語の寛政の頃には松平定信の改革により日蘭貿易はかなり収縮している。またナポレオン戦争のためバタビア(ジャカルタ)は長崎渡航の蘭船の確保も困難になって来た。市街の人口も3万人に減っている。そのためケンペルが言うほどの巨額の収入が大通詞にまだあったとは思えない。それでも通詞社会トップの4人しかいない大通詞の1人だから堀門十郎は立派な屋敷住まいであったろうと思われる。大通詞は近在の郷に別宅を持っていた例もあるから富裕であったことは間違いない。彼は1793年(寛政5年)に島津重豪が始めた書誌編纂事業の一つ「成形図説」の編集に関わっていたとみられる(『島津重豪』(芳即正 11p)。「成形図説」とは百科全書の日本版であった。ルソー等のフランス啓蒙思想は、世の万物すべてに光を当てる百科全書編纂を流行させ、探検家や旅行家は動植物地誌のすべてを記録するのが当時の習わしだった。シンガポール建国の父と称されるスタンフォード・ラッフルズは「JAVA」(ジャワ)についての貴重な百科全書を残したし、シーボルトの日本滞在の真の目的は日本についての百科全書をまとめることだった。「解体新書」のプロジェクトもこの流れに位置づけられる。オランダを通じてこのような事情に通じていた島津重豪は自力でこの日本最初の百科全書つくりに挑んだ。それが全70巻とも言われる(火事により大半が焼失した)「成形図説」の編纂である。当時一流の識者を呼び集め、世界に通じるものしようと文章にはオランダ語訳をつけた。
この物語の寛政の頃には松平定信の改革により日蘭貿易はかなり収縮している。またナポレオン戦争のためバタビア(ジャカルタ)は長崎渡航の蘭船の確保も困難になって来た。市街の人口も3万人に減っている。そのためケンペルが言うほどの巨額の収入が大通詞にまだあったとは思えない。それでも通詞社会トップの4人しかいない大通詞の1人だから堀門十郎は立派な屋敷住まいであったろうと思われる。大通詞は近在の郷に別宅を持っていた例もあるから富裕であったことは間違いない。彼は1793年(寛政5年)に島津重豪が始めた書誌編纂事業の一つ「成形図説」の編集に関わっていたとみられる(『島津重豪』(芳即正 11p)。「成形図説」とは百科全書の日本版であった。ルソー等のフランス啓蒙思想は、世の万物すべてに光を当てる百科全書編纂を流行させ、探検家や旅行家は動植物地誌のすべてを記録するのが当時の習わしだった。シンガポール建国の父と称されるスタンフォード・ラッフルズは「JAVA」(ジャワ)についての貴重な百科全書を残したし、シーボルトの日本滞在の真の目的は日本についての百科全書をまとめることだった。「解体新書」のプロジェクトもこの流れに位置づけられる。オランダを通じてこのような事情に通じていた島津重豪は自力でこの日本最初の百科全書つくりに挑んだ。それが全70巻とも言われる(火事により大半が焼失した)「成形図説」の編纂である。当時一流の識者を呼び集め、世界に通じるものしようと文章にはオランダ語訳をつけた。
そのために大通詞の松村安之丞を薩摩藩に召し抱えた。当時の通詞社会で吉雄幸作と並び立つ英傑と言われた人物である。このヘッドハンティングと言い、日本初の百科全書編纂の大プロジェクトと言い、島津重豪は藩財政の危機は十分認識していながらも、やりたいことやらねばならないことについては歯止めが利かなくなる性格だったのではないか。開明的な君主としてその事績の数々は幕末に雄藩として日本を導いてゆく薩摩藩を育て上げたと言えるが、同時に借財も天文学的に積みあがった。そういう意味では上杉鷹山の徹底的な倹約とは違う。ただ、散財するだけではなく、晩年に調所広郷を起用し財政改革を果たしたのだから帳尻は合わせたと言えようか。松村が薩摩に招聘された後、長崎在住の大通詞として島津重豪が目をかけたのが堀門十郎であった。「成形図説」の編纂が始まる寛政5年の1年前にヘンミイが長崎に着任している。島津重豪はヘンミイとも親交を深めている。「成形図説」編纂について堀門十郎がヘンミイに助言を求めることが多かったろうと推測される。西洋の百科全書に並び立つ「成形図説」にしようという意気込みが重豪にあったろうからだ。
名村恵助は小通詞末席という中堅通詞である。「大通詞-小通詞-小通詞並-小通詞末席-稽古通詞」(「阿蘭陀商館物語」宮永孝)という正規通詞の序列では中堅から軽輩のあたりである。これまでの文献、及びこの物語でも名村恵助を小通詞末席と扱ってきたが、2006年長崎在住の歴史研究家原田博二氏が画期的な論考『名村家の人々』を長崎の藤木文庫が発行する「崎陽」という雑誌に発表された。この論考をつい最近入手できたのでそれに準拠してこの先の物語を展開していきたい。原田氏が名村家の分限帳(職歴簿のようなもの)を詳細に調査したところによると、名村恵助は1785年(天明5年)に隠居し通詞の職を養子に譲っているのである。原田氏によれば「1785年3月直三郎(惠助の別名)は、テイツイングたちに内通したとの理由で阿蘭陀通詞たちによって毒殺された」と当時の出島のオランダ人たちが信じていたとオランダの日本研究家が発表したというのだ。だがこれは間違いで、惠助は隠居したのでオランダ商館に顔を見せられなくなったがそれをオランダ人たちが仲間に毒殺されたと思い込んだらしい、という。ティチングとは1779年、1781年、1784年と3回にわたって来日して商館長を務めた人物で島津重豪や桂川甫周など当時の一流の人々との親交も幅広く、後にロンドンで「日本風俗図誌」を刊行して、当時有数の日本通として知られた人である。前述したように当時は百科全書派の熱が世界を席巻していた時代である。出島にやって来たオランダ人(オランダ人だけでなくヨーロッパ各地からオランダ人と称して出島へやって来た)やティチングは、それぞれ極東の日本についての百科全書を編纂しようという野心を持っていたのである。その流れの中でシーボルトもこの後の1823年(文政6年)来日したのだ。彼らは動植物や地誌の情報を積極的に集めた。だが日本の情報、中でも国防上の機密である地図などの流出を幕府は極端に恐れ厳重に禁じた。それを承知でシーボルトは資料を密かに収集したが、彼を最高の知識人と崇める人々は喜んで求められるものを提供したようだ。それが江戸で明るみに出て(これも幕府の密偵の働きであったろう)大量の処分者を出したのがシーボルト事件である。
ティチングも事情は全く同じだったろう。資料収集の手足となったのが名村恵助のようだ。その名村を危なっかしい動きと通詞社会は判断したのだろう、彼を密かに隠居に追い込んだ。顔を見せなくなったので「毒殺された」と出島のオランダ人たちは思いこんだのだ。出島のオランダ人たちは終始監視の目に晒されている。ドゥーフの章で紹介したように、ドゥーフの自伝にはspyという言葉が7回も登場する。彼らは通詞そのものがスパイの役目を果たしていると理解していて決して心を許さなかった。監視されていたのはオランダ人だけではない。通詞にも通詞目付がいて通詞を監視しているし、長崎奉行所さえ江戸からの目付が目を光らせている。そういう中で忽然と姿を消した名村恵助を「毒殺」と判断したのはいかにも密謀と暗殺の歴史が渦巻くヨーロッパで揉まれたオランダ人らしいと言える。崎陽という明るい響きの別称を持つエキゾチックな国際都市長崎には陰湿な闇の世界もあったのだ。名村恵助が隠居して7年、ヘンミイが商館長として赴任してきた。すぐに島津重豪との親交が始まる。やがて二人の間でそれぞれのニーズを巡って密やかな盟約が生まれる。島津重豪側は堀門十郎がその意をヘンミイに伝えるのだが、大通詞という立場であってもいつも自由に商館長に会える訳ではない。出島の前の高さ13ⅿの丘には長崎奉行所西役所が聳えているから、そこからも出入りは丸見えである。そこで堀は隠居していた名村恵助に目を付けたと思える。名村恵助は養子が跡を継いだといっても通詞社会の一番下の稽古通詞である。経済的には裕福とは言えなかったろう。小遣い稼ぎに堀の使い番になったのだろう。堀はこのころ(寛政9年か10年ごろ)既に薩摩藩に召し抱えられていた可能性もある。成形図説の編纂の進捗もあったろう。そうすると長崎と薩摩を往来していたかも知れない。もしそうだとすると長崎で自由に動ける手足、つまり名村恵助の存在が便利になる。そしてさらに堀と名村は同じ町内の忠蔵に目を付けたのだろう。忠蔵はヘンミイの部屋働きであったから毎日出島に出勤する。出島に入った人間は、出島を出る時は門で待ち構えている探り番のチェックを受ける。探り棒というもので袂や懐を探るのである。原田博二氏資料にある忠蔵の判決文には「横文字其外かひたんより恵助江之礼物等取次遣し」とあるから、【島津重豪⇔堀門十郎⇔名村恵助⇔忠蔵⇔ヘンミイ】の流れで密約が形成されてゆく。忠蔵はヘンミイから預かったオランダ語の密書(というかメモ書きていどのものか)を、名村や堀からの入れ知恵で探り番を躱して今籠町へ持ち出しそこで名村に渡し、名村は文面を確かめて堀へ渡したものと思える。重豪からの返事は逆の流れでヘンミイへ届くことになる。1797年(寛政9年)、この密謀が大きく前進する出来事が起こった。1796年はナポレオン戦争のために1隻のオランダ船も来なかったのだが、1797年7月に2年振りに現れたオランダ船は実はアメリカ船を偽装した傭船であり、船長はアメリカ人のあのスチュワートだったのだ。スチュワートを迎えたヘンミイは天祐だろ思ったに違いない。オランダ人の船長と違い、スチュワートはオランダ東インド会社に何の忠誠心も持っていないだろう。彼と直接会って話をすれば、儲け話に乗ってくる冒険心に満ちた男だと気が付いたに違いない。こうして島津重豪とヘンミイの抜け荷プロジェクトは急速に具体化してゆく。翌年の1798年(寛政10年)もう一度スチュワートを傭船として雇い、長崎に来る途上に薩摩沖の海上で瀬取り(仲買)を行うという計画だ。ヘンミイは11月末にバタビア(ジャカルタ)へ戻るスチュワートに「来年もこの船長を傭船として契約するよう」にバタビアのオランダ東インド会社に依頼する手紙を託したのである。彼等は気が付いていないが、そのさなかの1795年(寛政7年)の夏に近藤重蔵が長崎に着任し、探索を始める。
当初は唐人へは外国事情調査と称し、またオランダ人へは西洋の植物や産物の調査と称して唐人館や出島に出入りし、実際にその優秀な頭脳を駆使して何冊もの書物を編纂してゆく。百科全書編纂が目的と聞けば、オランダ人も警戒を緩めたろう。そのうちに近藤重蔵はそれらの書物の編纂を進めてオランダ人の信頼を得、本来の目的の探索にかかったことだろう。おそらくは「西洋の本草や風俗を聞く」と称してヘンミイやラス、その他のオランダ人の部屋にも出入りしたのではないか。そしてあらかじめ見当をつけたのが、今篭町のトライアングルではなかろうか。探索にあたり、まず目を付けたのが堀門十郎の動きであったろう。そこから名村恵助と忠蔵の繋がりが浮かび上がってくる。そして動かぬ証拠を掴んだと思われる。彼が発見した決定的な証拠は何だったのか?それは闇に葬られて決して表に出てこない。が、その情報を基にヘンミイの参府旅行中は厳重に監視の目が注がれ、彼が病死したらすぐに行李の中を検(あらた)めて名村が寄越した「海中にて中買」の手紙が発見されることになる。こうして近藤重蔵の役目は終わる。1797年(寛政9年)の暮、近藤重蔵は長崎奉行所出役を解かれ、江戸へ戻る。栄転である。呼び戻したのは長崎奉行をその年の2月に交代して江戸へ戻っていた前奉行の中川忠英(ただてる)である。江戸へ戻った近藤重蔵は志願して蝦夷地の探検を引き受ける。千島列島にロシアが忍び寄ってきていたからだ。そして翌1798年(寛政10年)択捉島に「大日本恵土呂府」の碑を立てて日本史に名を残すことになる。
だが近藤重蔵が掴んだ情報は余りにも巨大過ぎるものだった。現将軍家斉の岳父自らが(岳父になってはや10年。しかも家斉も重豪も壮健で早晩引退の気配もない)国禁の抜け荷を指揮しているとは口が裂けても公にできないことだったろう。島津重豪には指一本触れられない。またヘンミイにも手出しができない。神君家康公、“ゴンゲンサマ”(ドゥーフが自伝で紹介した、家康が長崎で呼ばれている表現)から御朱印状を貰っている存在である。アンタッチャブルなのだ。過去にも商館長が抜け荷に関係した例はあるが、商館長そのものへは表立って手を出したことはない。どうするか?オランダ人が名村恵助がそうされたと思い込んだこと、すなわち毒殺によるヘンミイの排除ではなかったろうか?
1797年(寛政9年)夏、スチュワートがオランダの傭船としてイライザオブニューヨーク号で長崎に入港する。彼の滞在は数か月に及ぶ。彼を見込んだヘンミイの判断で、スチュワートが「海中にて中買い」役を引き受けることになり抜け荷の計画は急速に具体化してゆく。忠蔵と名村恵助、堀門十郎のトライアングルの動きが活発化する。それを密かに探索して密謀の全体図と証拠を掴む近藤重蔵。
この頃からヘンミイの体調が悪化する。下痢嘔吐が続き、体力が弱ってゆく。翌年の1798年(寛政10年)の正月には商館長最大のイベント江戸参府が待っている。将軍に謁見するのだ。だがヘンミイは体調不良を理由に夏までの延期を願い出る。だが幕閣は許さない。予定通り上京しろというのだ。その頃、近藤重蔵は栄転して長崎を離れる。こうして1797年は暮れ、翌年の正月、ヘンミイは江戸へ出発した。その留守の3月、出島が大火に襲われ、大変の建物が焼失する。その不吉な知らせはいつヘンミイに届いただろうか。ヘンミイは将軍謁見の帰途に掛川で帰らぬ人となる。享年50歳。「9章 陰謀渦巻く出島へ」で触れたように、下痢嘔吐が続いたヘンミイの最期はヒ素で毒殺されたナポレオンの症状に極めて近い。殺鼠剤として普及しているヒ素は最も入手が簡単で効果のある毒薬である。ヘンミイが江戸を発つときに江戸郊外で島津重豪がお忍びで現れる。ラスRasの日記によると(「抜け荷」山脇悌二朗116p)ヘンミイは乗り物を降りて重豪公に近寄り挨拶したが、この会話を通訳したのは既に島津重豪の配下になっていた堀門十郎であったそうだ。密談である。また島津重豪もオランダ語を話せる。何が話し合われたのか?ラスは重豪公が病気見舞いとこの先の旅の無事を祈ったというが、重豪ほどの人物である。背後の状況を分かっていて、ヘンミイに別れを告げに来たのではないか。あるいはこの先起こる筈の「海中での中買」工作の謝辞であったのかもしれない。ヘンミイが掛川の宿で亡くなると間髪入れず行李が探索されて名村恵助の手紙が押収された。近藤重蔵の探索で手紙の存在が確認されていたのだろう。
その2か月後の8月名村恵助と忠蔵は逮捕され、年の暮れの12月25日、クリスマスの日に名村恵助は市中引き回しの末、出島門前で磔となる。
忠蔵は死罪、斬首刑である。名村恵助のような市中引き回しの上での磔刑ではない。同じ死刑でもやや刑が軽いことになる。原田博二氏資料にある名村恵助の判決文は、「寛政10年)午八月晦日入牢 同十二月二十五日伺之上傑 右之者都而阿蘭陀人江内通等致し候儀は重キ御制禁二而持渡之品々日本之相場等仮初二もロ出合致問鋪段は元通詞を勤相弁乍罷在部屋働忠蔵を以手本薬種等迄差遣度々文通致し殊当春参府御断申上度旨之内談等は不軽儀二有之処狸二存寄申教遣し謝礼等貰請候段重々不届至極二付伺之上戸田采女正殿依御下知傑申付候」である。注目すべき点が二つある。罪科が「忠蔵を使って薬種などを渡し謝礼を貰った」他に、「この春の江戸参府を断るなどの相談をした」と江戸参府の件を殊更重く見ている点である。これは磔の真相である島津重豪絡みの抜け荷を公にしないためであろう。判決文では一切抜け荷の密議などの容疑は語られていない。揉み消したのである。もうひとつは「伺いの上」という言葉である。死罪以上の重罪は長崎奉行の独断では出来ず、幕閣に「伺いの上」刑を確定したことである。これは厳密な法治主義が行き届いていたことを意味する。また忠蔵は「寛政1 0 年 午八月晦日入牢 同十二月二十五日伺之上死罪 右之者日々阿簡陀屋鋪江罷出隠物持出入御厳禁二有之段は乍弁かひたん井元通詞名村恵助より被頼度々双方より内通之横文字其外かひたんより恵助江之礼物等取次遣し既二以右者重キ御法度之筋又は不軽内談二有之右之始末不届至極二付伺之上戸田采女正殿依御下知死罪申付候」と死罪となった。磔と死罪、この差は何だろう。ヘンミイは死んだが、残ったオランダ人への公然たる警告として通詞の名村恵助を出島の門前で名村恵助を磔にしたことは明白だ。ドゥーフをはじめ後世のオランダ人はこのあと決して抜け荷に関わらなくなった。また通詞社会への警告でもあったろう。磔を見たラスは恐らく恐怖のあまり腑抜けになったことであろう。面白いのは名村恵助の養子の稽古通詞名村喜三郎は「寛政10年)午九月朔日所預同十二月二十五日放役 右之者養父恵助儀阿簡陀人江内通致し候儀二付遂吟味処若輩二而何事も不弁趣無相違相聞候得共恵助儀右鉢重キ御法度を相背御仕置申付候付其方儀も放役申付候」と「放役」、つまり通詞を首になっただけで連座しなかったことである。若いうえに何も知らなかったということで罪を問われなかった。犯科帳の他の判決にも見受けられるが、江戸幕府の法治は意外と人情的な計らいがあるのも特徴的である。但し「名村恵助が相続した名村初左衛門家は、名村家の本家であったが(中略)断絶したものと考えられる」(原田博二氏論考)。平戸以来の通詞の名門は名村家の本家は断絶に追いこまれたようだが分家と別家は無事生き延びたようだ。余談ではあるが、近藤重蔵の晩年は息子の重罪の連座により近江国大溝藩に配流(はいる)という処分を受けた。長男が敷地の争いから町民7人を切り殺して八丈島に流罪になったからである。これも面白い処分である。喜三郎は父の犯罪であるから放役で済んだが、近藤重蔵の場合は息子の犯罪であるから親の責任を問われた。これが徳川幕府の法治観である。配流先の大溝藩では「このような小藩に当代一の知識人が来た」と藩主が受け止め、牢屋敷に閉じ込めながらも丁重に扱い本も許され藩士の教育もしたということである(近藤重蔵wiki)。もうひとつわかることは、御家人であろうと町民を殺せば罪を問われたことだ。これも幕府の治世が厳密な法治主義であったことの証左である。ただ身分の違いがあるから、7人も殺していながら死罪ではなく流罪になったことである。町民の側に落ち度があったのだろうか。
堀門十郎は薩摩へ脱出し逃げおおせた。「事件の直後、堀門十郎は、いち早く脱走して、伊勢長島の城主増山弾正正賢の家臣、春木観(南湖)のもとに潜伏したようである。春木は、天明の末年から寛政年代へかけて、正賢の命によって、長崎で画を学んだ人で、その時、堀と親交があった」(「抜け荷」山脇悌二朗116p)、という。だが事件から6年後の(1804年)文化元年「成形図説」が出版されるが、その蕃語(外国語)記載責任者として堀愛生という名がある(「島津重豪」(芳即正 143p)。島津重豪の重要プロジェクト完成のために幕府から追われている堀門十郎の名前を変え、何食わぬ顔をして仕事を継続させていたことがこれでわかる。島津重豪はやはり相当なしたたか者である。
さて、では「海中にて中買い」スキームの最も重要なキャスト、スチュワートはどうしたのか?これまで見てきたようにこの島津重豪とオランダ商館長を巻き込んだ「海中にて中買」スキームは1798年(寛政10年)ヘンミイの死とその後の幕府と長崎奉行所による関係者の処罰で、公然化することなく闇に消えた。だがスチュワートがこのスキームに加担することになったのは前年であり、スチュワートはヘンミイの「このアメリカ人の船長を来年も傭船として長崎へ寄越すように」とのメッセージを携えてバタビア(ジャカルタ)に帰っており、ヘンミイの願いは聞き入れられて翌1798年スチュワートは再度長崎へ現れる。だがそれはヘンミイの死後であり、スチュワートの長崎到着後ほどなくして名村恵助と忠蔵が捕縛されている。当然スチュワートは闇の計画については一切口を噤んだだろう。この時にスチュワートは薩摩で「中買」して長崎へ来たのかどうか。しかも商館長は代理のラスである。頼りにはならなかったろう。ラスは帳簿の記録はほとんどやらず杜撰ではあったがラスの日記は残っているのがスチュワート研究家であるGourlay教授の論文にある。しかし私には残念ながらこれを入手する手立てがない。だから薩摩での「中買」があったかどうかの真相はわからない。15章で述べたように、私の推理では1798年の2度目の来航の時にヘンミイと詳しく打ち合わせし、翌1799年に2隻で来航しスチュワートは途上「中買」する計画ではなかったか、とも思える。だが15章で解説したように1798年の帰途、スチュワートの船は長崎港口の高鉾島で座礁沈没し、スチュワートは長崎で正月を迎え、村井喜右衛門が奇跡的にイライザ号を引き揚げたのちバタビア(ジャカルタ)へは戻らず姿を消した。ではスチュワートと薩摩はそれっきりだったのだろうか。実はそうではない。このピカレスク(悪漢)スチュワートは薩摩との取引の痕跡を見せるのである。それを次章で検討しよう。